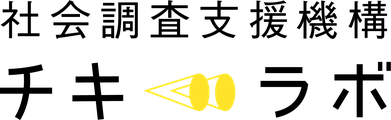昨年夏に起きた「令和の米騒動」。あれからも米の価格は上がり続けています。
農林水産省のデータを見ると、昨年の「米騒動」は8月に入ってから起きていました。南海トラフ地震臨時情報(8月8日発表) 、その後の地震、台風等の影響等も重なり、一気に米の重要が伸び、8月25日にピークが到来。例年、この時期には米の販売量は伸びますが、1年前に比べ販売量がさらに増加。例年以上に需要が高まったことも、米不足が深刻化した一因であることが推測できます。

図1 令和6年6月以降のスーパーでの米の販売数量・価格の推移
(出典:農林水産省 「スーパーでの販売数量・価格の推移(POSデータ全国)」)
チキラボはその「令和の米騒動」勃発直後の2024年9月30日〜10月2日にかけて、米の購買行動について調査をしていました。この時期に購買行動をとった人たちがどのくらい存在したのか。どのような情報に触れて米を購買したのか。データから読み解きます。
※この記事で引用するデータはチキラボの定期調査「社会抑うつ度調査」の第13回目の一部です。調査の概要・調査手法・第13回調査の回答者の基本データの説明はこちらをご覧ください▽
Ⅰ.「普段より多めに/早めに米を買った」は1割
まず、全体の傾向を確認しましょう。「あなたは、米不足が話題となった今年の8月から9月にかけて、普段より多めに/早めにお米を買いましたか?」との質問に対して、意外にも、全体の68.7%が「買わなかった」と回答しています。
反対に、全体の25.6%の人が、普段と異なる購買行動をとっています。そのうち、実際に米を購入できた人は、13.0%。全体でみれば、1割程度の人が、普段以上の購買へとつながっていました。そして「買おうとしたが買えなかった」人は、全体の12.6%。こうした人の行動も、米の需給バランスに変化を与えた可能性があります。

図2 2024年8・9月の「普段より多め/早めに米を買ったか」に対する回答(N=846)
Ⅱ.なぜ、普段以上に米を買ったのかーー米不足情報との接触
ではなぜ、普段以上に米を買おうとする行動が現れたのでしょうか。実際に米を「買った」「買おうとしたが買えなかった」という購買行動をとった層217名に絞って、その理由を複数選択可能な形で選んでもらいました。

図3 「早め/多めに米を買った理由」に対する回答(N=217)
すると、「米不足のテレビニュース」の影響力が37.3%で、比較的大きかったと確認できます。ネット(16.1%)、新聞(9.2%)、ラジオ(3.7%)等の影響力はテレビより小さいものの、それでも相応のインパクトがあります。
対して、実際に「スーパーの棚で米が少なくなっているのを見たため」との回答が45.2%と、選択肢の中では最も高い数字となっています。
また、「うちにある米がこのタイミングで切れたため/切れそうだったため」との回答も38.2%で、上から2番目の選択率でした。
さらに、「大きな地震が続いたため」(15.2%)、(南海トラフの)「巨大地震情報(注意)が出たため」(11.5%)、相次いでいた「台風が気になったため」(11.1%)などの災害備蓄や、「物価高がさらに続きそうなため」(15.2%)などを選んだ人もいました。
こうしてみると、「米の買い込みを促進するような状況」(地震や台風の災害、インフレなど)×「米不足を感じさせる情報(米のない商品棚、ニュース報道など)」×「米の購買が必要な状況」(家のストック切れ、家族からのうながしなど)が重なり、普段以上の米購買行動に出ていたことがうかがえます。
今回の備蓄米の放出は、どのような効果を発揮するのでしょうか。長期的には、マクロ目線の分析や農業政策の検証も必要です。他方で短期的には、実際に米が棚に並び始め、報道や口コミなども含めて「米不足が解消される」という予期が広がるかどうかが注目されます。
【引用資料】農林水産省 令和7年3月17日「スーパーでの販売数量・価格の推移(POSデータ全国)」(https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/r6_kome_ryutu-103.pdf 取得日2025/3/18)
【謝辞】調査票の設計・データ整理・集計表の作成は大川明李さんにご協力をいただきました。